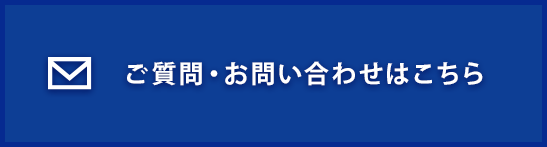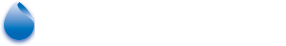チラー配管とは?種類や特徴、接続方法を簡単に解説
冷却などに欠かせないチラーですが、本体とともに配管も重要です。
今回はチラーの配管ついて、種類や特徴、接続方法について解説します。
チラーに関する知識を深めたい方は、ぜひチェックしてください。

チラーとは?
チラーとは、工場や機械操作において、いろいろな機械の冷却や保温に使われる装置の総称です。
英語の「Chill(冷やす)」という言葉から、派生したといわれています。
温度を上げる目的で使用されることもありますが多くは冷却に用いられており、一般的にチラーというと、冷却装置を示すことが多いです。
チラーは、主に液体を循環させて温度調整を行うものと、空気で温度を調整するものの2種類に分けられます。
急速に冷やすという用途には、液体を循環させるタイプが用いられます。
チラーを導入することによって、地下水を使って温度調整をした場合に比べて、結露がなくなるというメリットがあります。
また水道水を使って冷却するために多くなる水道代の節約にもなります。
さらに、空気での冷却は、夏など温度の高い時期は、外気温によって部品に負担がかかり寿命が短くなってしまうので、そういった場面でもチラーを導入すれば安定した温度調整ができるという点もメリットとして挙げられます。
チラー配管とは
チラー配管は、温度調整が必要な設備に、確実に冷却水を運び一定の温度を保つうえで重要な役割を持っています。
配管がうまくいっていなければ、途中で液漏れや温度変化が起こり、しっかりと冷却をすることができない可能性が出てきます。
配管というと、身近なところではエアコンのダクトホースや水道用のホースを思い浮かべていただければいいでしょう。
専門的なところでは、地下にある上下水道の土管、石油などのパイプラインがあります。
チラー配管の種類やその特徴とサイズについて
チラー配管の場合、ホースやプラスチックの素材のものは、耐久性や耐圧性が劣るという問題があります。
特に工場などの大きな設備では、耐久性が重要になるので、チラー配管ではこれらの素材はほとんど用いられません。
それでは実際に、チラー配管で使われる種類とその特徴をまとめましょう。
金属管
金属管の大きな特徴はやはり優れた耐久性と耐圧性でしょう。
炭素を含んだ合金で作られた炭素鋼鋼管は、最も多くの配管に使用されています。
耐食性の高いメッキ加工で、耐圧性が高い加工もやりやすく安価であるという点が評価されています。
錆に強いステンレス鋼管は、給湯や冷温水などの水を使用する場で用いられています。
アルミパイプは、非鉄金属の代表格であり、軽くてさびにくいのが特徴です。
熱伝導率も高いので、船舶の部品や熱交換器によく用いられています。
アルミニウムは、純度が高ければ高いほど強度が低く、用途に合わせて用いる場を変えています。
同じ非鉄金属の中でも、給水、給湯管や医療ガス配管、空調配管には銅管が用いられます。
熱伝導率や耐食性に優れているのはもちろんのこと、柔らかく加工しやすいという特徴があるので、複雑な配管場所でも適用できるのが魅力です。
樹脂管
樹脂管は軽量なうえ、接続や切断がしやすいため、工場のような大きな場所よりも、住宅用途や水道設備に使われることが多いです。
硬質塩化ビニル管や架橋ポリエチレン管などがそれにあたります。
耐薬品性・耐震性・腐食性にも優れていて、さらに内面を液体がスムーズに通過できるという特徴もあります。
ライニング管
ライニング管は、金属管に高い耐食性を持つ樹脂素材を接着したものです。
接着のことをライニングということからこうした名称になっています。
塩化ビニルやポリエチレン、ノンタールエポキシなどがライニングに使われ、消火栓や上水道に用いられています。
チラー配管にはサイズ選びも重要
チラー配管ではサイズ選びも重要です。
サイズによって、配管の中を輸送できる最大流量が変わってくるからです。
配管のサイズは3つの呼び方があって、それぞれ寸法が違います。
チラー配管をするときにはあらかじめ寸法の確認をしておきましょう。
そして、国内生産の配管と輸入配管では、規格が違う可能性があることも覚えておきましょう。
国内生産はJIS規格ですが、輸入配管はANSI規格になっているので、注意が必要です。
チラー配管の接続方法について
チラー配管は、種類の選び方も大切ですが、その接続方法も無視できません。
使い方に合わせた接続方法を行わないと、効率よく冷却ができません。
チラー配管の接続方法についていくつか紹介しましょう。
ねじ込み接続
これはチラー配管の接続方法で、もっとも一般的な方法がねじ込み接続です。
雄ねじと雌ねじをそれぞれねじ込む形で接続します。
ねじの規格が国内生産のものはほとんど同じなので、部材の統一がしやすいことと、部材が小型で軽量、取り扱いやすいうえにコストがかからないという点がメリットといえるでしょう。
その反面、ねじ込み部分が緩みやすく、液体が漏れる可能性があるということで、高圧の用途には向いていないというデメリットもあります。
チラー配管では、液体を流すことがほとんどのため、高圧でなくとも漏れには注意が必要です。
継ぎ目に隙間ができた場合、シールテープや液状シールを使うといいでしょう。
フランジ接続
配管はどこかの部分でトラブルが起こった時に、分解がしやすいフランジ接続も有効です。
フランジという板を使ってねじで結合することからこの呼び方になっていますが、配管の脱着が比較的容易で、強度もあるというメリットがあります。
トラブルが起こった時に、配管全部を外すことなく、ピンポイントでのメンテナンスができる一方で、コストがかかる・規格が統一されていない・溶接が必要などのデメリットもあります。
溶接接続
配管同士を溶接で直接接続する方法です。
耐久性が高いということで、高温高圧下のパイプラインに用いられることが多いです。
同じサイズの配管同士を突き合わせて溶接する方法と、雌型ソケットに配管を差し込んで溶接する方法とがあります。
コストが抑えられるというメリットもありますが、技術的な仕上がりにばらつきが出るというデメリットもあります。
樹脂管などの接続には、接着接続という方法も用いられます。
まとめ
チラー配管は、その場所や用途によって種類と接続方法が変わってきます。
コストの問題や配管をする場所にもよりますが、配管後にトラブルが起こらないよう、導入前によく業者に相談することをおすすめします。
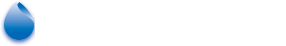


 English
English